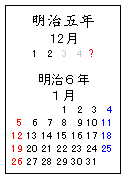 「今月の満月はいつ?」と聞かれたら、あなたはすぐに答えられますか? しかし明治5年より前の日本人ならば、みんな「15日に決まってる!」と答えたことでしょう。12月3日は「カレンダーの日」です。
「今月の満月はいつ?」と聞かれたら、あなたはすぐに答えられますか? しかし明治5年より前の日本人ならば、みんな「15日に決まってる!」と答えたことでしょう。12月3日は「カレンダーの日」です。「明治改暦」と呼ばれる暦の制度の変更が、明治5年(1872年)のこの日(になるはずだった日?)実施されました。それまでに使用されていた暦の12月3日に当たる日が、新しい暦の明治6年1月1日になったのです。
現在の日本の暦は、太陽の運行(実際には太陽のまわりを回る地球の運動)だけにもとづく太陽暦のなかの「グレゴリオ暦」を使用しています。明治改暦が行われた明治5年までは「太陰太陽暦」(通称旧暦、正式には天保暦)が使用されていました。
太陰太陽暦は、月の運行と太陽の運行両方にもとづく暦で、新月が月の最初(朔日=一日)になり、1カ月は29日または30日でした。1年は355日になり、そのままでは暦と季節にずれができるため、およそ3年に1度、閏月を加えて調整しました。したがって1年が13カ月になる年もあったのです。
太陰太陽暦では1年の月の数が違ったりするデメリットもありますが、月の満ち欠けがわかりやすいのが特徴です。明治改暦以来、日本には正式な太陰太陽暦は存在しませんが、「お月見」などはもちろん、潮の満ち引きなどに関係する多くの伝統行事が、現在でも旧暦にもとづいて行われています。
ところで明治改暦が行われた明治5年は、12月2日の次が翌年の1月1日になったので、1年が少し短くなりました。政府は2日しかなかった12月分の月給を役人に払わなくてすんだそうです。明治改暦には、「日本の暦を世界で広く使用されている暦に統一する」という目的があったのは事実ですが、当時の財源が苦しかったことも制度を改訂した理由の一つだというのです。本当はどうだったんでしょうね。
ちなみに、12月3日は旧暦で10月15日です。満月はこの晩(正確な時刻は4日0時19分)なのです。日が暮れるとすぐ、東からまん丸い月が上ってきますよ。
(中学生対象web原稿より怪鳥)